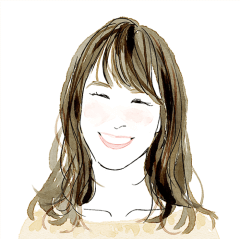心に悩みや不安を抱えた人の話を聴き、サポートする心理カウンセラーのお仕事。深刻な話やネガティブな感情と向き合いつづけてつらくないか、気になる方も多いでしょう。
今回は心理カウンセラーの城川先生の経験談と、心理カウンセラーが病まないための対処法についてお話をお聞きしました。
人の話ばかり聴いてしんどくならないの?
重い話ばかりでしんどいのではと思われがち
よく「人の話ばかり聴いてしんどくならないの?」と聞かれますが、そう心配するのは友人や知人の話を親身になって聴いている優しい人だったり、愚痴ばかり聞かされて辛い思いをしたことがある人なのかもしれません。
イメージとしては暗くて重い話ばかりで、ズーンと沈み込んでいる感じとか、愛憎のドロドロした話でもうたくさんというような、なんとも絶望的な感じでしょうか。
しんどく感じることもあるけれど、時々!
一般に友人の愚痴をきいていてしんどくなるのは、話が重すぎる、長すぎるときではないでしょうか。
カウンセラーは話の重さに関しては、同感ではなく共感を持ちいることで受け止め、長さに関しては1回50分などの枠組みで境界線を引いていているため、普通はしんどくなりません。
※「共感」について、詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
それでもあまりに強い憎悪や、同じ話を長期間にわたって繰り返されると、時折「しんどいな」と感じることはあります。ただ、むしろその「しんどさ」を、自分の中で見つめ、適切な形で次の一歩につなげることができればそれが転期になることもあります。
経験談・事例
カウンセラーのしんどさがヒントに
例えば、前の職場をパワハラで泣く泣く辞めることになった相談者の方がいました。カウンセリングをしても、激しい恨みが何ヶ月もにわたって繰り返されたときは、自分の中でも打ちのめされた感じや無力感を感じざるを得ませんでした。
スーパーバイザー(※)に相談すると、「その自分の受けた感じは、相談者が感じているものそのものではないか」「恨みが単純に無くなれば良いのではなく、恨みがあることで保たれているものがあるはずだ」と言われました。
(※ スーパーバイザーについて、詳しくは後述します)
相談者にカウンセラー自身の感じを伝えると、まさに、怒りで気づかなかったが、本当は無力感でいっぱいで孤独でつらいことにはじめて気づいたとのことでした。
さらに「恨みは持っていてよい、無理になくさなくてよい」ことを伝えると、恨みがあることで今、次に進めていない自分を正当化しているのだとご自身で気づかれていったことがありました。
このように、カウンセラーの中に生まれるしんどさは相談者を理解することにつながり、次の手がかりになることもあると思われます。
身体がしんどいと訴えたことも!
私自身がしんどさで胃痛と耳鳴りに苦しんだ時期もあります。
カウンセリングを1日で30分枠×15回実施する機関にいたころ、週1勤務のころはよかったのですが、週3に増やして(※週2は他の機関で働いていました)半年後、急に胃が痛くなり、耳鳴りもして、どうにも動けなくなってしまうことがありました。
体の検査は異常なしで、1週間ほどの休養で回復しました。自分のメンタルにはかなり気をつけていましたが、知らず知らずのうちに負荷がかかっていたようです。
私自身のカウンセリングのスタンスとして、じっくり丁寧に聴きたい、どちらかというと落ち着いてセラピーに取り組みたいタイプだったので、せわしない30分枠というのが合っていなかったというのが大きな原因でした。
今は90分枠、または60分枠でじっくり関われるカウンセリング機関におり、充実して働けています。
もちろん元の職場で週5で長期間働いているカウンセラーもおりますので、何より自分のスタンスや体力に合わせて職場選びをするのがいいのだと思います。
心理カウンセラーが病まないために必要なことは?
自分のしんどさに気づくこと!
カウンセラーとして相手の気持ちを受け止める以上、自分のしんどさにも敏感に気づく必要があると思います。
そのために「今、自分のしんどさは100でいうといくつかな」「今の元気度は100でいうとどうかな」とスケーリングすると少し客観的になれるかもしれません。
普段はどうしても目の前の仕事に集中しているので忘れてしまうのですが、ちょっと振り返ってみると、疲労感がもう限界に近かったということもあるものです。
私自身、調子が良いと思っていたけれど、疲れ具合をスケーリングしたら意外にも80ぐらいたまっていて自分でも驚いた、ということもあります。気づくことができれば、そこから自分を大事にする行動をとることができますね。
自分を大事にする!
カウンセリングは非常に集中力を使うので、知らず知らずのうちに疲労がたまっていることも多いものです。
マッサージやヨガなど自分をいたわったり、おいしいものを食べる、親しい友人と話す、旅行をする、読書をする、趣味を大事にするなど、自分が楽しめることをたくさんやってあげてください。
自分を大事にケアしてあげれば、余裕が生まれ、よいカウンセリングにつながりますし、相談者のモデルにもなるでしょう。
思い返せば、私が体調を崩す前あたりから、週末は疲れ果てて寝て過ごしていましたが、自分の楽しみを楽しむエネルギーが無くなっていたのは黄色信号でした。好きなことを楽しめているかも自分を知る良いバロメーターですね。
スーパーバイザーをもつこと!
スーパーバイズとは、知識や経験豊富な専門家にケースについて相談し、次の一歩を一緒に考えてもらうことです。
自分の中にため込んでしまうと、どうしたらいいかわからないまま次の面接を迎えてしまったり、情報量が多すぎて整理されないことがあります。そこをしっかり相談することで、問題がクリアになり、次にやるべきことがわかり、自信を取り戻せます。
ダメ出しされそうで少し怖いかもしれませんが、私が出会ったスーパーバイザーさんは皆優しくて、話すだけで癒され、それでいてケースの今後の道筋に気づけるようにしてくださる素晴らしい方ばかりでした。
1人でかかえこまず、専門家の力を遠慮なく借りましょう。
現役カウンセラーの立場から伝えたいこと
少なからず人のネガティブな面に触れるカウンセラー。もともと誰かの役に立ちたい気持ちが強く、自分より相手のことを大切にする傾向があったり、頼まれると断れなかったり、「大丈夫です」と言って限界まで頑張ってしまう人が多いように思います。
カウンセラー自身が病まないために、
- 自分のしんどさを自覚すること
- 自分の気持ちも身体も意識して大事にしていくこと
- 無理なものは無理と断る勇気を持つこと
- スーパーバイザーに相談して自分1人でかかえこまないこと
などを心がけるといいのかなと思います。
自分を大事にすることが、長く働けることにつながり、結果多くの人の役に立てることにつながります。
【予算別】安くてお手軽に心理学を学べる方法
予算1,000~2,000円なら、本を読んでみる!

心理学に何となく興味はあるけど、
お金をかけて心理カウンセラーの資格を取るほどでもないかな...

そんなあなたは、心理学のマンガや入門書がおすすめです!
価格も1,000~2,000円程度でサクッと学べます!
「心理学に興味を持っているけど、お金をかけるほどの熱意はない。」という方は、初心者向けの入門書を読んでみましょう。
初心者向けの入門書は、堅苦しく専門用語が並ぶテキストではなく、はじめて心理の本を読む人に配慮した、構成やデザインになっています。マンガ形式のものもあるので、下記のリンクから探してみてください。